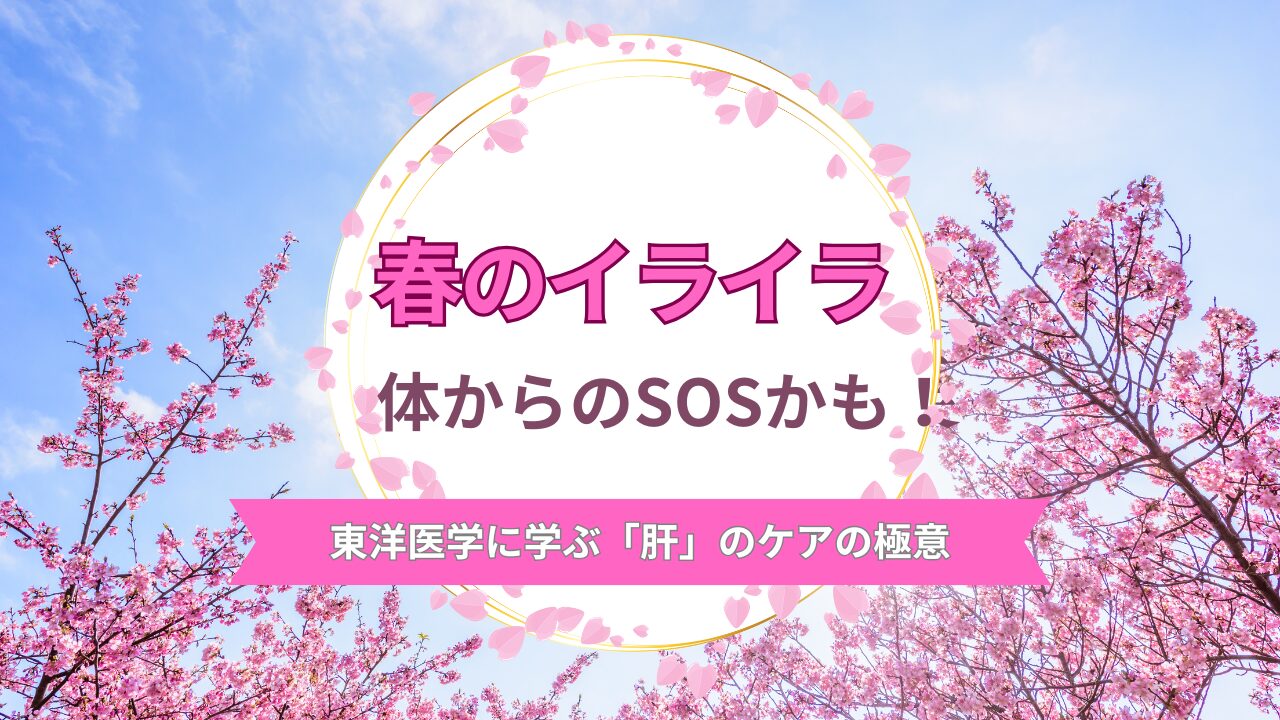
2025年02月19日
今年は(2025年)の2月は、想像以上に気温の差と風の強いこと。
関東では、17日は
昼前に最高気温15℃を超えたものの
夜遅くには7℃、場所によっては5℃
気温差が10℃もありました。
日本海側では大雪。
身体も対応しようと大変です。
東洋医学における「春」の始まり
東洋医学における「春」の始まりは、西洋の暦とは少し異なります。
少し、迷いますよね。
<二十四節気(東洋医学的な春)>
立春(2月4日頃)~立夏(5月5日頃)
東洋医学では 「春は立春から始まる」 と考えられます。

<一般的な春(気象的な春)>
3月~5月
気象庁などの基準では3月から春とされますが、東洋医学ではもっと早く始まると捉えます。

< 春のエネルギーの流れ>
東洋医学では、春は 「陽気が増え、体が冬のこもった状態から開放される季節」
そのため 2月上旬頃から少しずつ春の養生を始める のが理想的です。
春の特徴と東洋医学的な視点
春のエネルギー: 冬に蓄えたエネルギーが動き出し、万物が芽吹く季節。
東洋医学では「肝」の季節とされ、気血の巡りや情緒に影響を与えます。
-
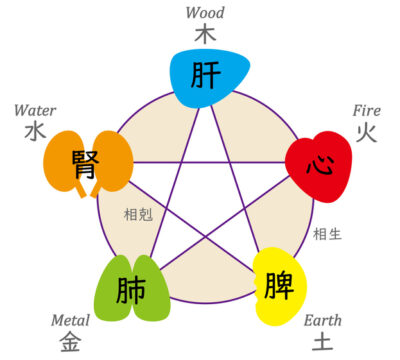
-
春の不調とその原因-
芽吹きの季節である春は気候も穏やかで過ごしやすく感じますが、進学、入社、引っ越しなど新しい環境が増える時期でもあります。
そのため、人は環境変化のストレスを受けることが多くなります。こうした環境の変化により感じるストレスにより体内を流れる「気」は停滞しやすくなります。
それによって気分の落ち込みやイライラ、おなかの張り、肩こりが起きやすくなります。

春は中医学的な内臓分類である「五臓」の一つ、「肝」に負担がかかりやすい季節であると考えられています。
「肝」には気や血(体内を流れるエネルギーや血液)を巡らせるという働きがあるため、「環境変化によるストレス」と「肝の働きの低下」という二つの要因により前述の症状が出ます。
また、春特有の失調として目の不調(ぼやけ、かすみ、眼精疲労)や筋肉のこわばりなどが出る、と中医学では考えます。

また、肝は「怒」の感情を支配すると中医学では考えており、肝の失調により怒りやすくなったり、怒りが溜まりやすくなったりすることにも注意が必要です。
-
春の養生法
食事
<肝を助ける食材>
苦味のある山菜(ふきのとう、菜の花)でデトックス
酸味のある食品(梅干し、柑橘類)で肝機能をサポート
気血を補う食品(ナツメ、ほうれん草、アサリ)
運動と活動
-
朝早く起きて軽い運動や散歩をすることで陽気を取り入れる。
無理なく体を伸ばすヨガやストレッチも有効。

心のケア
-
リラックス法(深呼吸、瞑想)でイライラを解消。
趣味や自然との触れ合いで心にゆとりを持つ。

睡眠
-
午後11時までに就寝し、午前1時~3時(肝が活発になる時間帯)にしっかり眠る。

朝は、早くに起きる。 -
春に注意したいポイント
-
急な薄着で風邪をひかないよう注意する。
「春は新しいことを始める最適な季節です。東洋医学の知恵を取り入れて、心身ともに健やかな春を過ごしましょう!」
